自分がクライアントのWebサイトをデザインする際に、気を付けている事・心掛けている事をご紹介します。
Web制作会社に勤めていた頃に先輩デザイナーから学んだ経験、そして数多くのWebサイトを制作してきて学んだ経験を元にしています。
意味のあるデザイン
デザインには何かしらの意味がなければいけません。どんな小さな意味でもいいんです。「どうしてデザインなの?」とクライアントに訊ねられたときにちゃんと即答できる状態が好ましいと考えます。
もちろん「このデザインが好きだからです」のような個人的な意見は除きます。
伝えたい事のランク付け
ヒアリングやディレクションから、クライアントがWebサイトでどのような事を伝えたいのかを読み取り、重要度でランク付けを行います。そのランクに基づいたデザインを行う。
商品の良さを伝える為にあえて人物画像を減らすなど、なんでも盛り込むプラスではなく、ときには要素を減らすことも必要です。
読み物として成立しているか?
Webサイトにおいて誰かに何かを伝える方法は文字(テキスト)が一番有効。
グラフィックデザインにこだわり過ぎて文字が少なくなっていなか?文字の可読性を損なうデザインになっていないか?など、「文字を読ませて伝える」という本来の目的が損なわれないデザインを心掛けています。
文字が与える印象
文字には、ゴシック、明朝、ポップ、手描きなど様々なフォント種類があります。そして、フォントによってユーザーが感じる印象も様々。
また、文字の太さや文字間を変えることで、全く違った印象を与える事もできます。サイトのデザインテイストに合わせて文字の調整も行います。
サイトテーマと色の関係
色使いはデザインの基本。制作するサイトテーマに沿った色を選ぶのはもちろん、使用する色の数にも注意しています。
そして、扱うジャンルによっても、使うとイメージアップにつながる色や、使ってはいけない色などもあります。
例えば医療などのジャンル。「赤色」を使っている病院のサイトはほとんどありません。なぜなら、一般的に、病院で赤色は血、つまり苦痛、痛みといった連想に至り、閲覧者にマイナスイメージを与えるからです。
逆に多くの病院サイトは白、青といった清潔感を連想させる色や、緑といった安心安全感を連想される色を取り入れています。
また、同じ赤系でも薄いピンクのような暖色系であれば、優しさや命を連想させるので、良いイメージにつながるでしょう。一見連想ゲームのように単純に思えるかもしれませんが、色が与える影響力は以外にも大きいという事なんです。
デザイナーとアーティストの違い
ジャンルは違いますが、インテリアデザイナーの森田恭通さんはこんな言葉を言っています。
デザイナーはアーティストではない
アーティストは自分を表現する
デザイナーは人の要望に応える
クライアントが存在するWebサイトデザインに、自我を出しすぎたり自分の意見を押し通すとこは、デザイナーのする事ではないということです。
自分の実績として作品づくりをしたいのであれば、勝手に自主制作をした方がいい。デザイナーとして仕事をする上での最低限理解しなければいけない事です。
その一方で、デザイナーとして絶対にやってはいけない事が、「全てお客さんの注文通りに作る」と言うこと。
矛盾しているようにも思えますが、これをやってしまうと、今度はデザイナーではなく単なるオペレーターになってしまいます。オペレーターとは言われた事ただ単にこなす作業員です。
デザイナーのあるべき姿とは、まずクライアントの要望を十分に理解すること。そして、その要望に沿ったデザインを作ること。
もしクライアントが納得いかない様子であればもちろん修正をする。あまりにも筋違いな修正を求められた場合は「デザインのプロ」という立場で、クライアントに説明し納得してもらう努力をする。
クライアントという依頼元があってのデザイナーとい立場をしっかり理解しつつ、クライアントが求めるデザイン、そして主旨と合致するデザインに近づける努力を怠ってはいけないと思います。
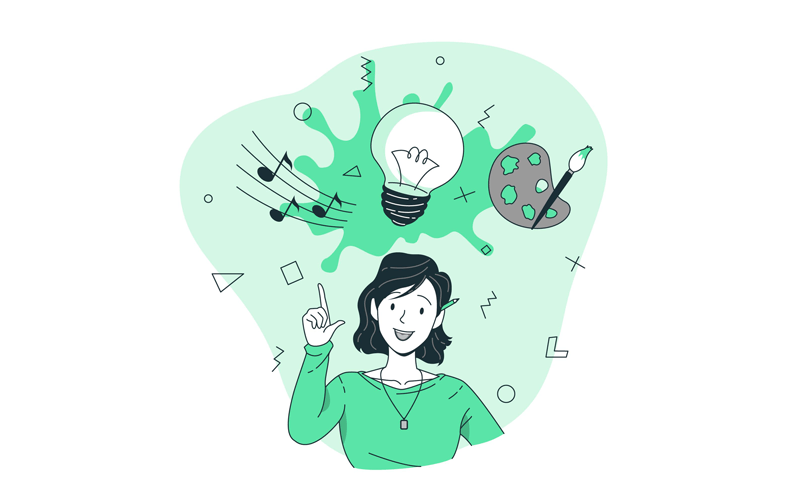

記事のコメント